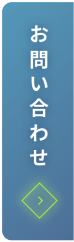2021.08.23
お知らせ・トピックス
医療法人の節税対策を検証
クリニック奮闘記のスピンオフ版としてまとめてみました。
節税対策として一般的に考えられていることが、思った効果を得られているかを検証してみます。
医療法人の節税対策
(クリニックの発展と医療法人化)
個人事業のクリニックの税金は、所得税の累進課税の適用を受けるため、高所得の院長先生にとってはその負担は極めて大きい。やがて事業規模が大きくなり、医療と経営の効率化を考える様になると、医療法人化に向かっていきます。そうなると、医療法人と個人間の所得分散が可能になり、全体としての税負担は軽減し、医療法人内に内部留保、経営の安定化へと繋がっていきます。
保険診療が中心のクリニックの場合、医業収益は安定しているため、基本的には黒字体質の経営になっている。そんなクリニックの院長の関心事の一つに『税金』がある。財務データの経費項目の中で目に付くのは、薬品仕入、外部検査費、人件費、家賃、リース料かもしれないが、『税金』はこれらの費目を大きく上回る額になっており、しかも直接的には、クリニックの経営には何の恩恵もないので文句の一つも出てくるのが分からなくもない。
(経営の安定化と納税)
納税したくないので設備投資をする院長がいます。確かに、支出が増えると利益が圧縮されますので納税は減ります。問題は、クリニックの経営にとって有益な投資か否かにあります。高額な医療機器であっても使わなければ宝の持ち腐れです。レントゲン室の隅っこや、処置室のベッドの奥に鎮座している器機はないでしょうか?経費を使うことで納税は減りますが、現金も減ります。無駄使いをするくらいなら納税して、現金として内部留保した方が経営的にはよいということになります。
※法人税率30%と仮定しています
☆何もしない場合
法人税額 :利益100万円×30%=30万円
キャッシュフロー:100万円-30万円=70万円 → 法人の内部留保になります
☆100万円の無駄使いをした場合
法人利益 :利益100万円-100万円(無駄使い)=0
法人税額 :ゼロ
キャシュフロー :100万円-100万円=0
(本当に節税対策になっているのか?)
前述した様に、納税額を減らすことと、キャッシュフロー経営はトレードオフの関係になる場合があります。レバレッジを効かせてキャッシュフローを最大化する手法はありますが、リスクが伴うためお薦めしません。一般的に節税対策として行ってる下記の事例について、『税金』と『キャッシュバリュー』の両方から効果を検証してみることにする。
① 中古車両の購入
節税の手法として車を購入する場合があります。
リセールバリューの高い某社で中古の超高級車を購入した場合の税効果を考えてみよう。
☆対象物件
中古購入価格3000万円(残価設定1000万円) 4年落ち
数年後に残価で売却した場合をシミュレーションする
4年オチの中古車の耐用年数は2年ですが、定率法により償却を行う場合は100%償却なので、購入時に一括損金処理が可能。(新車購入の場合は耐用年数6年で償却しますが、基本的な考え方は同じ)
・購入時の法人税の軽減分※法人税率30%と仮定しています3000万円×30%=▲900万円
・売却時の法人税負担分 1000万円×30%= 300万円
・車両購入による節税効果900万円-300万円=600万円
では車両を購入することによる所有コストは?
3000万円-1000万円(売却収入)-600万円(節税額)=1400万円
車両購入による節税効果はトータルで600万円となりますが、そのために1400万円の資金がキャッシャアウトします。これはキャッシュフロー経営の考え方としては合理的でないことは明らかですが、3000万円の超高級車を1400万円で所有することができたことに価値があるか否かと結論付けられます。購入した以上の金額で売却できなければコストが発生していることは明らかで、"得している"と思うことは妄想であると認識する必要がある。車検ごとに車を買い換えることで"車貧乏"になるのは是非とも避けたいところである。
(注)売却収入は消費税の課税売上になるため、自費診療収入と合算して1000万円以上になる場合は、消費税の納税義務が発生します。
(注)残価設定は売却時の車両の状態等により変動するため、上記シミュレーションによる保有コストが高くなることがあります。
② 生命保険を活用した節税対策の考え方
令和元年の法人税基本通達の改定により、法人生命保険契約における『課税の繰り延べ効果』が得られなくなった。これまでは医療法人の節税対策として有効な手法でしたが、生命保険の利用にあたっては、考え方をアップデートさせられることになる。
生命保険が持つ本来の保障機能は言うまでもないが、ここでは解約返戻金の取扱いについての基本的な考え方をお話ししたい。
・生命保険の入り口戦略と出口戦略
生命保険契約の法人税法上の取扱いは、最高解約返戻率の割合により細かく区分されている。(国税庁HP第3節 保険料等 定期保険等の保険料に相当多額の前払い保険料が含まれる場合の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)
結論から言うと、生命保険の持つ機能を最大限に発揮させるためには、目的に合わせた商品を選択しなければならないということです。では医療法人の生命保険の活用法として一般的な、役員退職金の積立について考えてみる。
考え方のポイントとしては、『医療法人の後継者の有無』にある。
1.医療法人に後継者がいる場合(M&Aを想定している場合)の選択肢・・・出口戦略
事業を継承する段階で、理事長退職金という損金が発生します。ポイントは退職金の受給時に解約返戻金の含み益が最大化できる様にするところにあります。契約時から解約時直前までは、損金処理の面でデメリットが生じますが、退職金としての受給におけるキャッシュバリューの最大化と、損金化による欠損金の繰越しにより法人税の圧縮効果を得ることもできます。
2.医療法人に後継者がいない場合・・・入口戦略
クリニックを閉院することを前提にした場合は、損金性に重視した生命保険が適しています。この場合、前述の様な解約返戻率は見込めませんが、保険料を損金化することにより保険本来の保障機能を低コストで得ることができます。
(まとめ)
第一に、特別償却や税額控除等の制度活用による節税を検討してみましょう。納税を減らすための支出については、長期的な視点にたって事業に役に立つか否かを検討しなければならない。設備投資をすることで短期的には納税は減りますが、長期的な生産効率(営業効率)が上がらなければ意味のある投資とはいえない。むしろ設備投資などせずに納税し、内部留保を蓄えた方が、コロナ禍の様な不測の事態にも備えることができる。
節税は最大限行うべきではありますが、先生方の視点は、経営効率の最大化に置かなければなりません。『納税』と『資金繰り』を両輪としてクリニック経営の舵取りを行って下さい。
【制度を利用した節税対策】
●医療機器の特別償却
・500万円以上の機器 14/100
・人工呼吸器、シリンジポンプ、インフルエンザ等対策装置 20/100
・生体情報モニター、分娩監視装置、特殊寝台ほか 20/100
●中小企業投資促進税制を用いた電子カルテの導入(税額控除、特別償却)
・160万円以上の全ての機器装置
・電子計算機、デジタル複合機 120万円以上
・ソフトウェア 70万円以上
※取得の場合 取得価額×7%の税額控除 もしくは、30%の特別償却
※リースの場合 リース費用総額より7%の税額控除